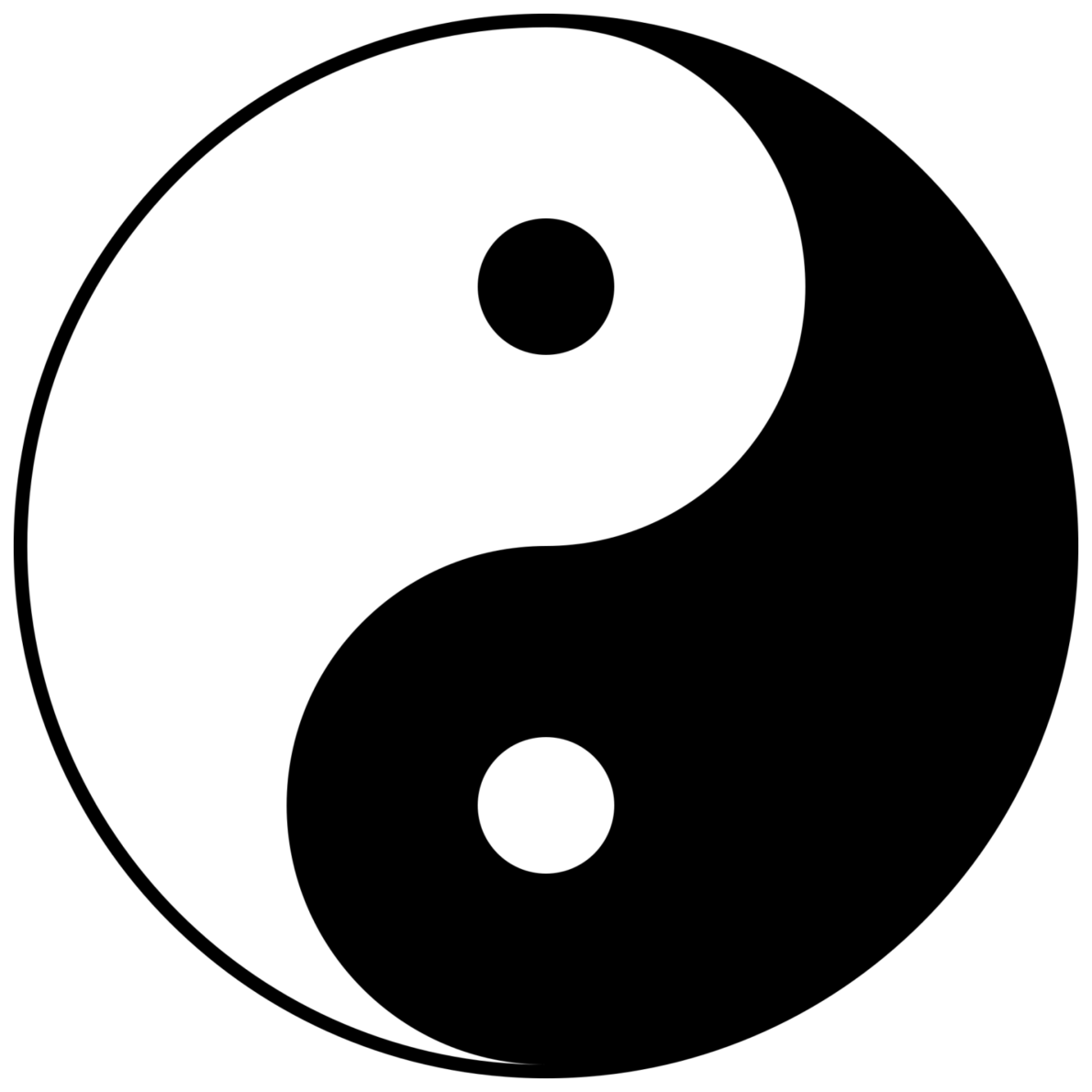◉火の輪と水の輪、そして永遠無限の和
十七条憲法の「和を以て貴しと為す」の一文にみられる〈和〉という言葉は「わ」と発音されるものです。「わ」の音からは「輪」という円環のイメージが想い浮かべられます。本稿では全十七条の読み解きにこれまで取り組んで参りましたが、この中に、二つの「輪」をイメージさせる条文があったことについて、ここで改めて考察してみたいと思います。
それは[第五条]と[第十条]の条文のなかにあります。
【第五条】
役人たちは飲み食いの貪りをやめ、物質的な欲をすてて、人民の訴訟を明白に裁かなければならない。人民のなす訴えは、一日に千軒にも及ぶほど多くあるものである。一日でさえそうであるのに、まして一年なり二年なりと、年を重ねてゆくならば、その数は測り知れないほど多くなる。このごろのありさまを見ると、訴訟を取り扱う役人たちは私利私欲を図るのがあたりまえとなって、賄賂を取って当事者の言い分をきいて、裁きをつけてしまう。だから財産のある人の訴えは、石を水の中に入れるようにたやすく目的を達成し、反対に貧乏な人の訴えは、水を石に投げかけるように、とても聴き入れられない。こういうわけであるから、貧乏人は何をたよりにしてよいのか、さっぱりわからなくなってしまう。こんなことでは、君に使える官たる者の道が欠けてくるのである。
【第十条】
心の中で恨みに思うな。目に角を立てて怒るな。他人が自分にさからったからとて激怒せぬようにせよ。 人にはそれぞれ思うところがあり、その心は自分のことを正しいと考える執着がある。他人が正しいと考えることを自分はまちがっていると考え、自分が正しいと考えることを他人はまちがっていると考える。しかし自分がかならずしも聖者なのではなく、また他人がかならずしも愚者なのでもない。両方ともに凡夫にすぎないのである。正しいとか、まちがっているとかいう道理を、どうして定められようか。おたがいに賢者であったり愚者であったりすることは、ちょうどみみがね〈鐶〉のどこが初めでどこが終わりだか、端のないようなものである。それゆえに、他人が自分に対して怒ることがあっても、むしろ自分に過失がなかったかどうかを反省せよ。また自分の考えが道理にあっていると思っても、多くの人びとの意見を尊重して同じように行動せよ。
これら二つの条文に見られる二つの輪とは、第五条に見られる「水紋(水の輪)」と、第十条に見られる「鐶(鉄の輪)」です。
[第五条]には、水に石を投げ入れるという表現があることから、水面に現れる円環の水紋がイメージされます。石を投げ入れた直後には、水面に同心円の模様が現れますが、それは永続的なものではありません。すぐに消えてなくなる、はかない円環です。[第五条]の主題とするところは、人間の煩悩の一つである「貪欲(むさぼり)」です。仏教では、人間の欲望を示すものとして「水」の表現が用いられることが知られています。
それに対して、[第十条]の主題とするところは「瞋恚(いかり)」の煩悩です。条文中にある「鐶(みみがね)」とはすなわち金属の輪であり、そこから連想されるのは「火」です。金属は火を用いて製錬されるものだからです。仏教では、人間の怒りの感情を示すものとして「火」の表現が用いられます。金属の輪は、内と外とを隔てて、端と端とが固く閉じているものであり、閉塞や対立という人間の心理状態を表すものと読み取られます。これは先に述べた「貪欲」の煩悩に対応して、「瞋恚」の煩悩を示しているように受け取られます。
ここに見られる条文には、『法華義疏』のなかでも太子が精緻な解釈をなされている「譬え」や「方便」の方法論を取り入れた、隠喩的な表現技法が読み取られます。
持続しない形状の「水紋」も、閉塞して開かない「鐶」も、太子が理想とされる「和」を譬えるには相応しくありません。けれども、渦巻き状のらせんを描く上昇する輪であれば、どうでしょう。それは永遠に向上してつながり、無限に拡大してひろがっていくイメージになります。らせん状の「輪環」に端はなく、永遠に失われることもありません。太子が理想とされる「和」のイメージとは、「らせんを描く永遠無限向上の循環」だったのではないでしょうか。
憲法の[第三条]には「天は覆い、地は載す。四時(しいじ)順(したが)い行いて、万気通うことを得(う)」という一節があります。これは、天は覆い、地は載せる。そのように分の守りがあるから、春・夏・秋・冬の四季が順調に移り行き、万物がそれぞれに発展するのである と訳されるものです。
また[第十五条]には、「上和下睦」の文言があります。これは、上下ともに和らいで協力せよ と訳されるものです。
ここに見られる、天地や上下といった、二つの相反する要素が一つに交わり、自然のめぐりに順って「和合」するイメージは、道教に見られる「陰陽」の図像に譬えられるものではないでしょうか。