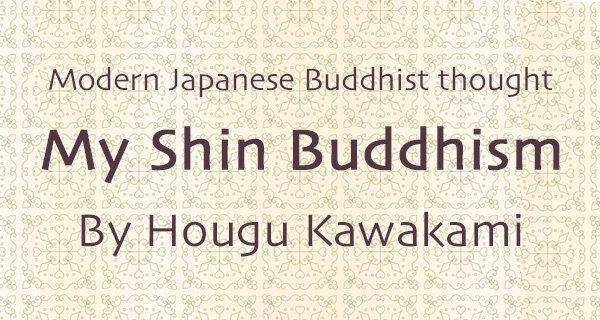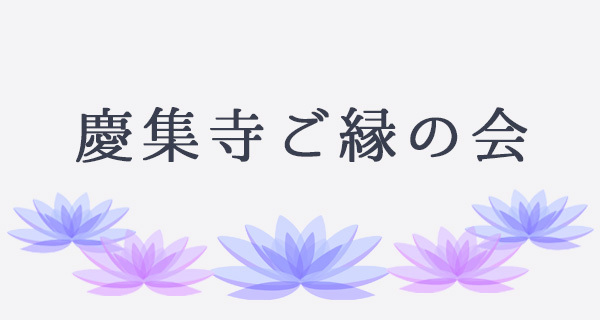-
序 ①そもそも、神さま?仏さま?
「神だのみ 仏だのみ」や「神も仏もありゃしない」などという言い方があります。神棚も仏壇も神社もお寺も、旧来より引き継がれてきた地域・親族の慣習や、ならわし・しきたりとして、これまで伝えられてきたからでしょうか。一般的な日本人の宗教観として、神さまも仏さまもいっしょくたにして語る部分があるようです。深く考えることもなく、当たり前のようになんとなくある「神さま」そして「仏さま」。けれども、宗教の主と
-
序 ③仏は如来と同じ
天台宗や真言宗、禅宗、日蓮宗、浄土宗、そして浄土真宗など、日本の仏教にはさまざまな宗派があり、それぞれの宗派で、礼拝の対象となるご本尊が定められています。すべての宗派に共通する礼拝の対象は釈迦牟尼仏、いわゆる「お釈迦さま」です。しかしながら他にも、阿弥陀仏、大日仏、薬師仏など、さまざまな仏さまがいらっしゃいます。仏教は一つであっても、様々な捉え方があって、仏さまと言っても多様にあるということです
-
Ⅰ仏法(1)ダルマに目覚めたブッダ
さて、まずそもそも仏教とはどのような宗教かということを確認しておくと、読んで字の如く「仏の教え」すなわち「ブッダの教え」です。キリスト教がイエス・キリスト、イスラーム教がムハンマドというように、仏教という宗教にもそれを開いた始祖がいるわけで、それが「ブッダ」であるということです。前回述べましたように、仏教には多様な仏(ブッダ)があるわけですが、ここで言うブッダとは、歴史的に実在した人物「ゴータマ
-
Ⅰ仏法(2)ブッダたちの伝えてきたダルマ
ブッダといえば仏教の信仰対象を指す用語という認識が、現代では一般的であるように思われます。しかしながらゴータマ・ブッダの生存された古代インドの時代に立ち返ってみると、必ずしもそれは仏教固有のものではなかったようです。仏教学者の並川孝儀氏が著された『ブッダたちの仏教(ちくま新書 2017年)』には、「ブッダ(buddha)」という語は、仏教で初めて現れる用語ではなく、すでにインドの聖典『ヴェーダ』や『ウパニ
-
Ⅰ仏法(3)ブッダのダルマの多様性
仏教の基本姿勢は「対機説法」であると言われています。様々な人々の状況や能力に応じて、相手に相応しい言葉で教えを説くということです。それはまた「応病与薬」とも言われます。相手の苦しみの現状に応じて、それを楽にするための教えを説くのが、仏教であるということです。ゴータマ・ブッダは、45年間の伝道のなかで出会った人々の、それぞれの状況や能力に応じて様々な教えを説かれました。その教えが仏弟子たちの個性を
-
Ⅰ仏法(4)中村元の合理主義
近現代日本における「アヌブッダ(ブッダに従って目覚めたブッダ)」ともいうべき大学者・中村元先生の『佛教語大辞典(東京書籍)』と『合理主義-東と西のロジック-(青土社)』を頼りにして、「法(ダルマ)」とは如何なるものなのかについて考えていきたいと思います。 まずその項目の最初には、法とは「ダルマ(dharma)」の漢訳で、「保つもの」という意味の語根に由来する言葉であると記されています。そしてそれに続
-
Ⅰ仏法(5)人間の真実を語る仏法
前回『佛教語大辞典』を頼りとして紐解いた「法(ダルマ)」についてまとめると、人間が生きるにおいて普遍的な規範として保つべき合理的な法則。自然の道理。真理。といったほどの意味になると思います。しかしながらまた、ここで言われる「真理」が、人間の理性や知性の働きによる「ロジック(論理・論法・議論の道筋)」のような範疇に収まるものではないことも、前回に述べた通りです。 『佛教語大辞典』の法(ダルマ)
-
Ⅱ縁起(1)因果律と縁起の理法
今章ではまず、ブッダのダルマ「仏法」の基本として説かれる、因果律と縁起の理法について解説してみるところから始めてみたいと思います。 例えば、種を蒔いて、花が咲く。花が咲いて、実が成る。というのは、原因と結果の関係性を言っているもので、こうした見方を「因果律」といいます。種(A)→ 花(B)→ 実(C)Aがあるから、Bがある。Bがあるから、Cがある。というように、ある事象Cが引き起こされるための原因Bを探
-
Ⅱ縁起(2)思い込みと決め付け
仏法に説かれる縁起とは「因縁生起(いんねんしょうき)」が略された言葉です。ある現象が生起するには、それが起きるための直接的な条件となる原因だけではなく、間接的にはたらく様々な要因、すなわち「縁」がなくては成り立ち得ません。あらゆる存在や事象を形成するための諸条件が「縁」であるということです。様々な要因が関係し合って、この世の全ての事象や現象が起きている、成り立っているというのが「縁起」というもの
-
Ⅱ縁起(3)すべては移りゆくもの
数ある仏教用語の中でも「諸行無常」は耳なじみのある言葉だと思います。「諸行無常の響きあり」なんてフレーズを思い出す人もいるかもしれません。この仏教用語は、一般には「無常感」といった心情として受け取られることが多く、物事は移ろいやすく儚いものであるという情緒的な感性で、虚無感と同義に受け取られることが多いようです。しかしながら本来の意味でいうところの「諸行無常」とは、すべての物事は一時として止まる
-
Ⅱ縁起(4)誰の思うようにもなってない
私たちの世界における諸々の存在や現象は、いかなるものもすべて一時として止まることなく変化し続けています。物も変われば時代も変わり、人も変われば、心も変わっていきます。すべてのものごとは常に移り変わって行くものです。過去から現在へ、現在から未来へ。止まることも、戻ることもなく、時間はいつも進み続けています。これが諸行無常という事実であり、現実です。諸行無常は、世界の有り様を実際に観察すれば、誰もが
-
Ⅱ縁起(5)前世と来世、私の宿業
私たちは皆、呼吸をしながら、生きています。息を吸って、吐いてを繰り返しながら生きています。 人として、オギャーと泣いてこの世に生まれたときの最初の呼吸から始まって、一度吸った息は必ず吐かなければならず、それを吐き切る間もなくまた吸って、そしてまた吐いてを繰り返しながら生きています。自分が吸った息を、誰かが代わりに吐いてくれるということはありません。自分の吸った息は必ず自分で吐かなければ
-
Ⅱ縁起(6)宿命と運命
人それぞれの能力や性格というものは、人それぞれの生き方や環境によって育まれるものですが、持って生まれた先天的な能力や性格というものも、少なからずあるような気がします。自分が生まれてきた時代や地域、産みの親や生活環境によって、国籍、性別、肌や髪や目の色、経済状況などは人ぞれぞれに異なり、自分の意思で選んだわけではないことは多くあります。人生というものは、やはり「宿命」と言わざるを得ないものなのでし
-
Ⅱ縁起(7)あるようでない ないようである
諸行無常の「諸行」とは、この世に存在するすべての事象や現象や現実のことを言います。それに対して諸法無我の「諸法」とは、私たちの認識し得るこの世界の範囲を超えて、遍く、余す所なく、分け隔てなく、例外なく、すべてのあらゆる「あるがまま」をいうものです。それは目には見えない観念や意識の範疇にまでも及ぶものであって、それこそが真実の「ありのまま」そのものを示すものなのです。仏教では、すべてのものごとは関
-
Ⅱ縁起(8)すべては関わり合ってあるもの
ブッダの説かれた諸々の法(ダルマ)に通じる原理原則は、すなわち「無我」ということです。すべての事象や現象は、固定的絶対的にあるものではなく、縁起の道理に従って「何らかの関係性に依存してある」ということなのです。ものごとをありのままに観察してみるなら、このことは例外なくすべてに関して適合する事実であり、現実であるはずです。 ブッダのダルマに照らして考えるなら、本来の仏教において「霊魂」の
-
Ⅱ縁起(9)相補性原理と動的平衡
仏法(ブッダのダルマ)の基本的な原理として第一に挙げられるのが「諸行無常」です。それは、この世界のすべてのものが”変わり続ける”ということは、”変わらない”というものです。それを言い換えるなら、この世界で”変わらない”ことは”変わり続ける”ということでもあります。こうした考えは、一見矛盾しているようにも感じられることでしょう。しかしながらもう一つの基本原理である「諸法無我」に照らして考えるなら、固定的絶
-
Ⅱ縁起(10)自らの生き方は自らに由る
前述した生物学者の福岡伸一氏は、著書『動的平衡-生命はなぜそこに宿るのか-』のなかで、自然界の基底にある「時間」の概念にも以下のように言及されています。人間の記憶とは、脳のどこかにビデオテープのようなものが古い順に並んでいるのではなく、「想起した瞬間に作り出されている何ものか」なのである。つまり過去とは現在のことであり、懐かしいものがあるとすれば、それは過去が懐かしいのではなく、今、懐かしい
-
Ⅱ縁起(11)よいもわるいも縁は縁
自分が起こした行いの結果は自分の身に受けなければいけないということを「自業自得」と言います。また、よい行いをすればよい報いがあり悪い行いをすれば悪い報いがあるということを「因果応報」と言います。科学の公理でもある「因果律」は、原因があって結果があるという関係性をいうものであって、過去の自分の行いを原因として、現在の自分が結果としてあるということは、紛れもない事実です。しかしながら、自業自得
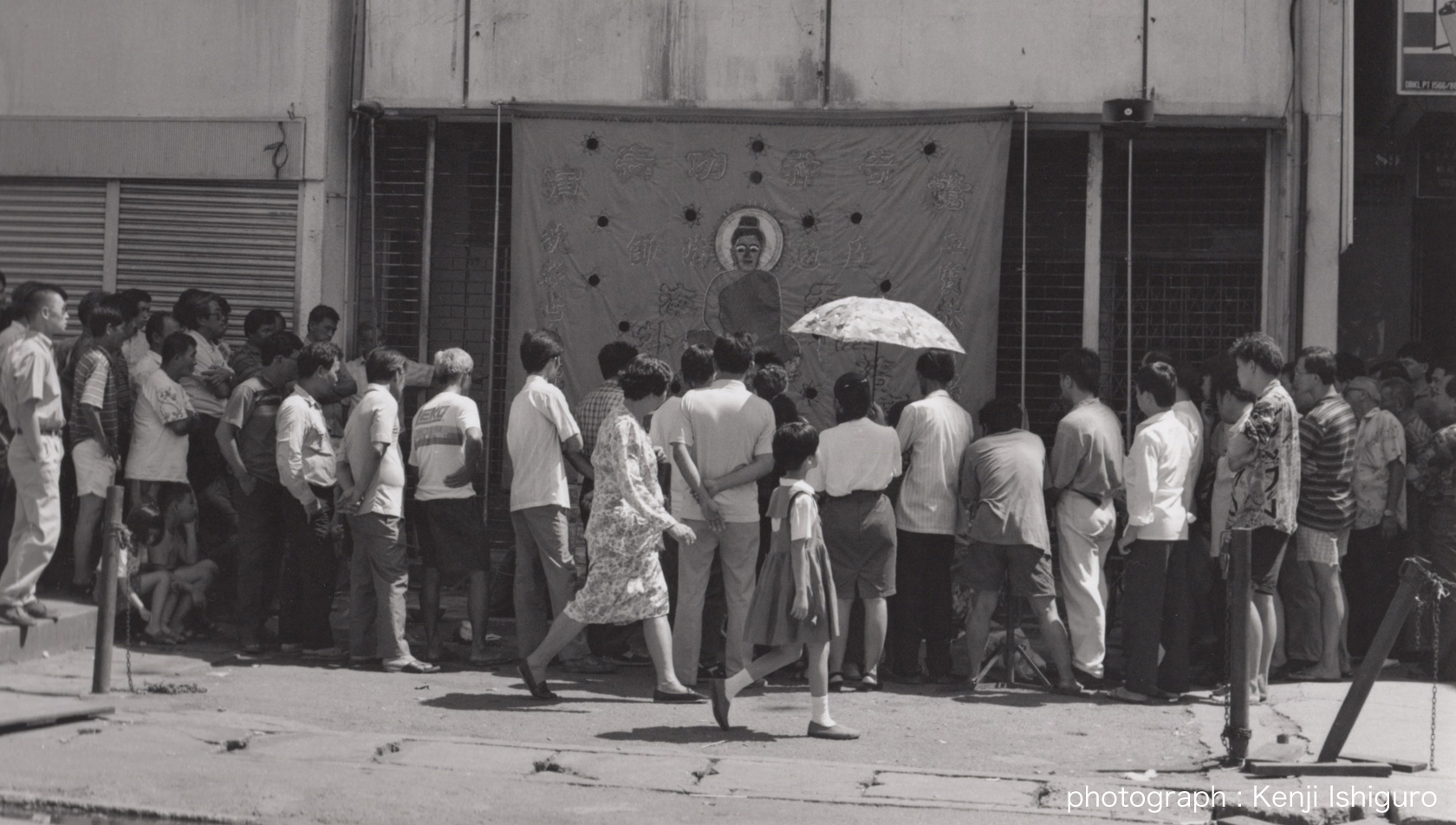
そもそものところから
腑に落ちるところまで
仏教に向き合って
考えてみたいと思います