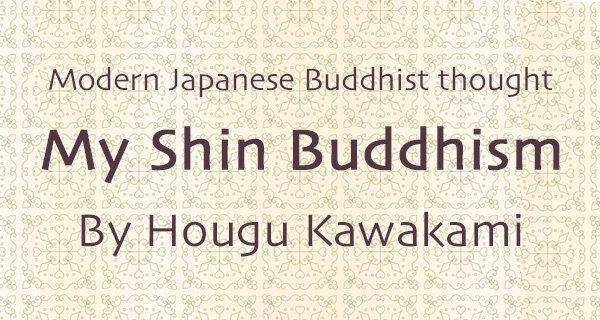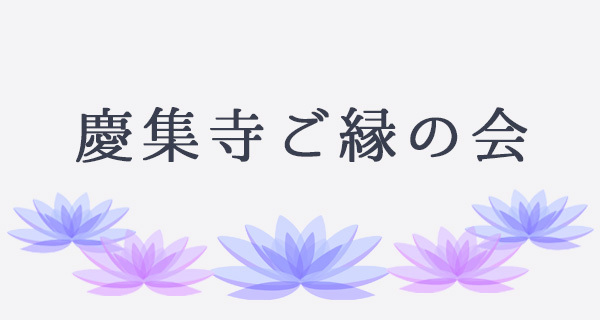光吸収率99.995%という、ほとんど真っ黒な、光を反射しない物質が米マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームによって発見されたといいます。けれども0.005%は光を反射するわけですから、それでは「完全な黒」とは言えません。それは「ほとんど黒」としかいえないものです。
有と無や、白と黒のような二項対立する概念と同様に、「光」と「闇」とを二つに分けて考えがちな私たちですが、「光」がつくり出すのはあくまでも「影」です。私たちが認識する世界には「明るいところ」と「暗いところ」があって、物に光が当たるとそこは明るく照らされるし、その反対に影をつくって暗くなるところもあります。けれども、その影のなかにも明暗のグラデーションをつくり出す、光が含まれているのです。影には光が含まれているのです。
光があるところには必ず影が生じるだけであって、光に対する闇が存在しているわけではありません。けれども私たち人間の思考の構造は、どうしても二つに分ける方法をとって、極端な断言をしがちなもののようです。二項対立する相対的で固定化した観念が、光に対する闇のようなものを想定してしまうのでしょう。
世界をありのままに見るなら、闇というものは私たちの外界にあるわけではなく、私たちの内側にあるように思われます。これを仏教では「無明」といいます。
「アミターバ(阿弥陀のひかり)」は、どんな心の闇をも打ち破ると説かれます。心の闇に、希望の光を差し込んで届けるのです。ゆえにこの光は[不断光]と称されます。その光は、時間的にも空間的にも観念的にも、何ものにも断たれることなく、すべてを常に照らしています。