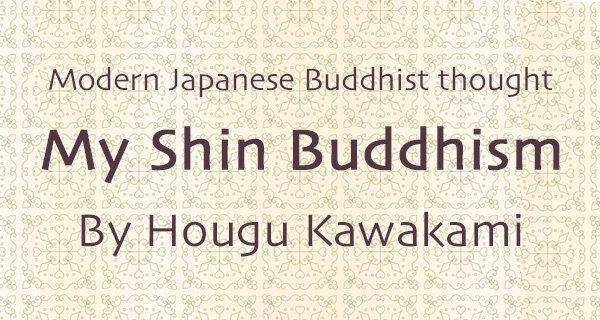私たちは皆、呼吸をしながら、生きています。
息を吸って、吐いてを繰り返しながら生きています。
人として、オギャーと泣いてこの世に生まれたときの最初の呼吸から始まって、一度吸った息は必ず吐かなければならず、それを吐き切る間もなくまた吸って、そしてまた吐いてを繰り返しながら生きています。
自分が吸った息を、誰かが代わりに吐いてくれるということはありません。
自分の吸った息は必ず自分で吐かなければいけないように、自分の為した行いの結果を直接受けるのは必ず自分です。今ある自分を形作る原因を為したのは、他でも無い、これまでの自分であるということです。
過去があるから現在があって、現在は未来に繋がっていきます。
自分の為してきた行いのことを「業(ごう・カルマ)」といいますが、一度起こした業は、それを原因として必ず何らかの結果を生み出すこととなり、その結果をまた業として、必ず何らかの結果を生み出し続けているのです。
つまりは、これまでに自分が為してきた行いの連鎖の結果として、現在の自分があるということです。今の自分を形成する直接的な要因としてあるのは、他でも無い、自分が起こしてきたこれまでの行為なのです。
この世に生まれてきた時に吸った最初の息があるのだから、もしかしたら、自分が生まれる前に吐いた最後の息があったかもしれない。
自分が死ぬ時に吐き切る最後の息の後には、もしかしたら、どこかの世界でまた最初の息を吸うことになるかもしれない。
因果という考え方から導き出されるものとして、そんな想定をすることも出来るでしょう。
自分が今生きている世界を「現世」として、その前に生きていたかもしれない世界を「前世」「過去世」または「宿世(しゅくせ・すくせ)」と言ったりします。また自分の死後に再び生まれ変わるかも知れない世界を「来世」とも言います。
前世や来世、輪廻転生といった考え方は、仏教発生以前の古代インドからあったと言われており、仏教の始祖であるゴータマ・ブッダにとっては、自らの思想を展開する際の前提としてある「社会通念」として受け取られていたものであったと考えられます。
現世に影響を与える業として、過去世において残された業のことを、仏教では「宿業(しゅくごう)」と言います。また、いまここに生きている自分は、過去世からの因縁によって定められた「宿命(しゅくめい)」を生きるものだとも考えられます。
確かに、自分が生まれてきた国や時代、産みの親や家庭環境、性別、肌や髪や目の色など、自分の意思で選んだわけではないことは多くあります。
能力や性格や体質などは、自分の努力次第で変えられるように言われたりもしますが、やはりどうしようもなく生まれつきある性質というものも、あるような気がしてなりません。
ひとの人生を羨ましく感じて、自分の「宿命」を恨みがましく感じさえもする、
そんな私たちです。
自分が為した行いがそのまま自分に返ってくるという意味の「因果応報(いんがおうほう)」や「自業自得(じごうじとく)」という言葉がありますが、どんなに受け入れ難い自分であったとしても、これを「宿命」と受け入れて、この世の自分を生きていくしかないのでしょうか?
自分の人生や未来は過去世からの業によって、
既に「宿命」として決められているものなのでしょうか?
宿命、そして運命に向き合い、考えてみたいと思います。

photograph: Kenji Ishiguro