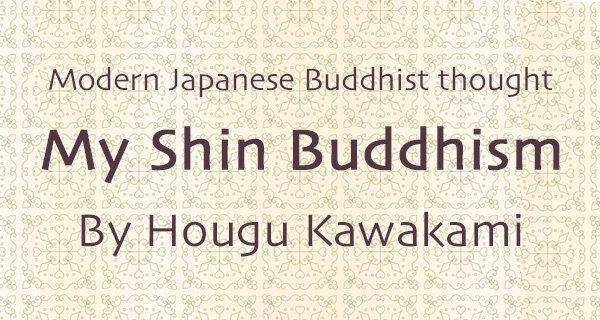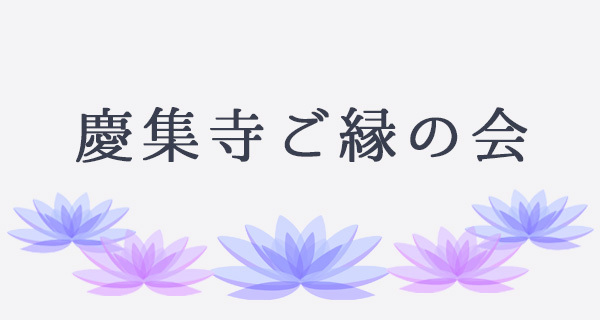近現代日本における「アヌブッダ(ブッダに従って目覚めたブッダ)」ともいうべき大学者・中村元先生の『佛教語大辞典(東京書籍)』と『合理主義-東と西のロジック-(青土社)』を頼りにして、「法(ダルマ)」とは如何なるものなのかについて考えていきたいと思います。
まずその項目の最初には、法とは「ダルマ(dharma)」の漢訳で、「保つもの」という意味の語根に由来する言葉であると記されています。
そしてそれに続いて、
①慣例。習慣。風習。
②なすべきこと。つとめ。義務。
③社会的秩序。社会制度。
といった語意が挙げられ、インドで一般に用いられている「法(ダルマ)」の意味としては、「行為の規範」「行為の規則」「人間の行為を保つもの」が元来の意味であると記されています。
西洋においては教祖や教団、経典に対する絶対的信仰がその拠り所として強調されるのに対して、インド人を代表とする東洋は、普遍的規範、すなわち「法(ダルマ)」を重要視して、それに従おうとする傾向があると言われます。
人と人との間に生きていかなければならない世間にあって、私たちは日々を右往左往しながら暮らしています。揺れ動く心と行いをブレないように保ち、為すべきことを為して生きていくためには、何らかの指標や指針であったり、「拠り所」となるものが必要になるのでしょう。
何でも自分の自由にやっていいとなると、逆にどうしていいか分からなくなるものかもしれません。これをしておけば大丈夫。というような「決まりごと」があった方が、案外生きやすいものなのかもしれません。
『佛教語大辞典』の法(ダルマ)の語彙説明には、上記に続けて
⑤真理。理法。普遍的意義のあることわり。 と記されています。
自分自身の人生における規範であり、他者や社会において共有し得る規範ということであれば、それは間違ったものや疑わしいものではなく、どんな状況にあっても、確かに信じることの出来る、普遍性のあるものでなくてはいけません。誤りではなく、正しいこと。嘘ではなく、本当のこと。偽ではなく、真であることの必要性があります。真であることこそ、真の「拠り所」とするべき価値のあることだということです。
真理とは、真実の理に適っていることをいいます。ある特定の時代や地域や文化においてのみ通用する一般常識や社会通念、伝説や神話への信仰のみを対象として絶対化するのでは、真理とは言えません。また、異なった宗教を信奉する者にとっても受け入れざるを得ないような論理性がないようであれば、真理ということは出来ません。
理に適うところまで思考を重ねて推理し、議論を尽くして合意を導くには、確かな思考の筋道で組み立てられた論理性が必要です。異なる主張を持った者同士が互いに合意するまで論理性が高められた地点でこそ、合理的な認識や判断が可能になります。もちろんそれは、科学的な「エビデンス(根拠・証拠・論証)」にも適応しているものでなければいけません。
あらゆる時代や地域や文化において、人間の理性や知性に適う形で、自然と心から頷くことのできる教えであってこそ、人類普遍の規範にもなり得る、真に「合理的な宗教」であるはずです。
合理主義という言葉からは、物事を理性的に割り切って考え、感覚や情緒に流されることなく、思慮分別による理知的な認識を第一とする立場のようにも感じられますが、中村元氏はその著書『合理主義-東と西のロジック-』のなかで、
経験を無視した合理主義は無意味である。
と断言されます。
合理主義というのは、自然または人間に関する「道理」に合することを目指すものであり、それは人間の理性に関することはもちろんのこと、感情・情緒・意欲・欲望といった感性に関することをも対象とした、人間の主体的な経験に基づく「合理」であるべきだと、中村先生は述べられます。
その上で、インド人が求めた「ダルマの宗教」に相応しいものが仏教であり、
このような宗教は、それ自身が合理主義的であると言い得るであろう。
と結論づけられます。
仏教とは、人間の理解を越える神秘的な事象をただ闇雲に信じることではありません。かといって、人間の理性を至上のものとして論理的批判的思考を尽くそうとする、倫理や哲学のようなものでもないのです。
自分のこととして現実をありのままに見るならば、人間の理性というものは、それほど頼りになるものではないような気がします。人間の激烈な感情や欲求の前では、理性のタガなんて簡単に外れてしまうのが。私たちの現実の有り様でしょう。分かっちゃいるけど、やめられないのが私たち人間なのです。
そしてまた、頭で理解したつもりなだけでは、心が頷くというところまではいかないのも人間でしょう。五臓六腑に染み渡るようにして、自分自身の経験や体験として、つくづくそうだと感じるところまで納得することができなければ、理に適うとまでは言えないものでしょう。
仏教とは、人間の理性と感性の両方に、頭と心の両方に、同時にしかも円満に働きかけて、同意と共感を及ぼすものなのです。
春夏秋冬は順番に巡ってくるものであって、その順番が入れ替わることはありません。どれだけ暑くなってもやがては涼しくなってくるものであって、ずっと寒くていつまでも暖かくならないということはありません。時間の経過とともに一日には必ず朝と昼と晩はあるものですから、夜明けの来ない夜はありません。出口のないトンネルはないといいますが、必ず光は差してくるはずです。
人間の不確かな理性によって固定化される認識や判断を絶対のものとするのではなく、自然の道理に適った誰もが同意と共感を示しうるのが「法(ダルマ)」です。
ただ理性に合するということではなく、物事が自然に合する筋道立ったものでなければいけない。人の道に反することなく心からもっともなことだと頷くことができなければ、それを「合理」とはいわない。そう中村先生は論じられているのです。
では、理性的認識を越えた「合理」として示される、法(ダルマ)とは? 真実とは?
更に掘り下げて、自らの腑に落ちるところまで考えてまいりましょう。
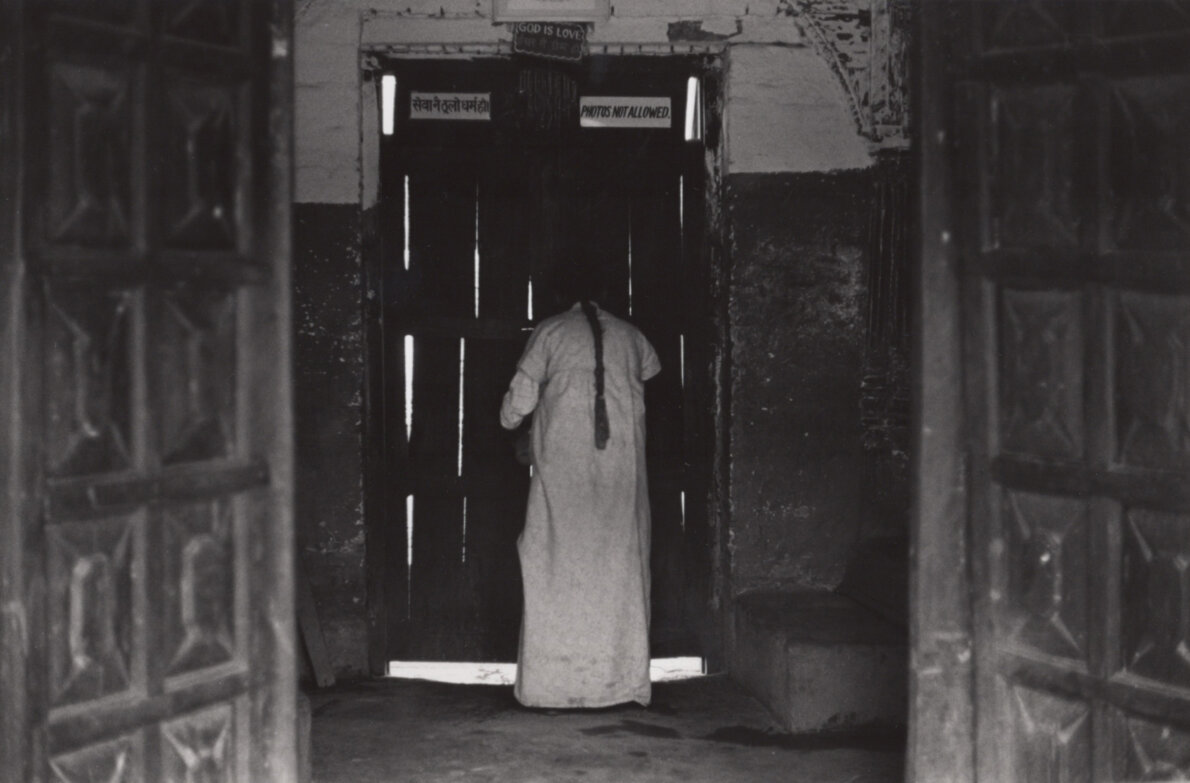 photograph: Kenji Ishiguro
photograph: Kenji Ishiguro