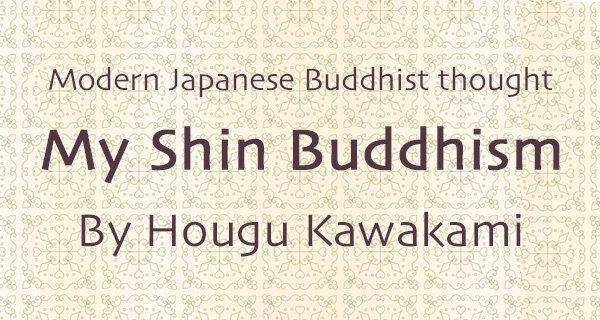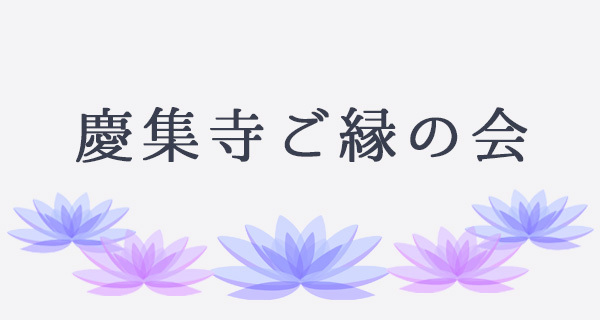-
① 親鸞聖人は自然葬を言い遺した
① 親鸞聖人は自然葬を言い遺した (自然法爾)浄土真宗の宗祖・親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、「私が死んだらその遺体は賀茂川に流して、魚のえさにしなさい」と言い遺されたといいます。近年では、自分のお葬式やお墓について生前中から計画を立てて準備をしておくことは「終活(しゅうかつ)」とも呼ばれてそれほど珍しくもありませんが、親鸞聖人の終活はいたってシンプルで、川に流してくれればそれでいいという
-
② お釈迦さまのご分骨の行方
② お釈迦さまのご分骨の行方 (仏法僧)約二千五百年ほど前のインドに生きられた釈尊(お釈迦さま)の場合はどうだったのでしょうか。お釈迦さまの死が間近に迫ってきたと感じられた時、弟子の一人が「先生の死に際して、私たちはその後の対処をどのようにすればいいのでしょうか?」と尋ねられたそうです。それに対してお釈迦さまは「僧侶(出家者)は葬儀に関わる必要はない。葬儀のことは町の人々にまかせて、ただ修行
-
③ 遺骨供養は自然な心情
③ 遺骨供養は自然な心情 ( お墓の歴史 )意外にも思われるかもしれませんが、お釈迦さまの説かれた仏教の本来の教えとは「霊魂」の存在を否定するところから始まっています。もう少し正確に言うなら、「霊魂」というものが固定的で不変的な実体としてあるかのように執着した考えを持つことは、人間が目指すべき真に自由な生き方には反するものだということを、仏教では説かれているのです。インドにあった本来の仏教には
-
④ 変わりゆく家とお墓
④ 変わりゆく家とお墓 (諸行無常・諸法無我)明治時代の家制度に基づく「一族の墓」は、戦後の新民法に基づく「家墓」として受け継がれながら一般にまで広く普及し、第二次世界大戦後の数十年の間でその数を急激に増やしていきました。けれども、時代の経過とともに家の形態も多様に変化していき、核家族化が進むとともに一つの家でも複数の世帯に分かれて、様々な生活形態が個別に営まれるようになったことも、現実的な
-
⑤ 遥かなるつながりと出遇いなおすところ
⑤ 遥かなるつながりと出遇いなおすところ (遠慶宿縁)私という一人がこの世に生まれてくるには、二人の人が必ず必要です。それは、一人の男性と一人の女性と言った方が良いかもしれません。父である人と、母である人とが出会ったことによって、私は生まれてきました。父という一人の人にも、父がいて母がいて、それは私にとっての祖父であり祖母でもあるわけですが、つまりは父が存在するにも、二人の人が必ずいたわけで
-
⑥ 共有の時代に共同のお寺のお墓
⑥ 共有の時代に共同のお寺のお墓 (倶会一処)私たちが日々を生きるこの世界は、ますます気忙しく世知辛く、生きづらいものになっているのかもしれません。何のために生きているのかわからなくなってしまうようなことも、時としてあるかもしれません。何を信じて何を心のよりどころとすればいいのか、多くの人がわからなくなってしまっているのかもしれません。信教の自由が保証されている現代では、人それぞれに何を信じ

時代劇のようなご時世であれば「死して屍(しかばね)拾うものなし」ということもあったかもしれません。けれども現代では、誰かが亡くなられたら、そのご遺骨がのこされますし、それをどこかへ葬らなければいけない、ご遺族ものこされます。ならわしやしきたりにとらわれることなく「葬送の在り方は自由」なのかもしれませんが、いざ「なんでもあり」となってみるとなると、どうすればいいのか? これからの葬送について、考えてみましょう。